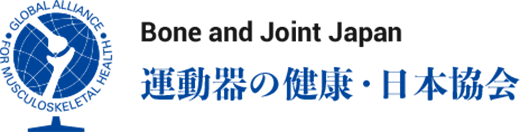「2025年度 第13回運動器の健康・日本賞」が能登半島地震による被災地で活動した「足元からの健康づくり 能登Foot活(復活)支援事業」に決定!

「運動器の健康・日本賞」は、公益財団法人運動器の健康・日本協会(Bone & Joint Japan・略称BJJ)が平成24年(2012年)より始めた“運動器の健康”を普及啓発推進事業の1つです。これまで12年間、全国の団体・機関および個人が行った「運動器の健康・推進活動」を募集し、審査によって、もっとも独創的かつ優れた活動を「運動器の健康・日本賞」として顕彰してきました。
今年は13年目。「2025年度第13回 運動器の健康・日本賞」は、昨年の2024年9月1日から募集を開始し、2025年1月10日までに計27件の応募がありました。2025年1月21日(火曜日)に審査委員会が開かれ、厳正なる審査の結果、最優秀賞の「運動器の健康・日本賞」には、2024年1月に起きた能登半島地震によって被災した石川県で活動を行った「足元からの健康づくり 能登Foot活(復活)支援事業」(石川県立大学体育学研究室 宮口和義、恵寿総合病院)に決定しました。他、優秀賞2件、奨励賞5件が決定しましたので、詳細は以下より閲覧ください。なお、「運動器の健康・日本賞」の主な概要を申請者よりご紹介します。
石川県立大学体育学研究室は2019年から能登の地域医療を支える恵寿総合病院「けいじゅヘルスケアシステム」と中高齢者を対象に草履サンダルを用いた足育活動、Foot活プロジェクト(高齢者の歩行を改善することで健康を取り戻す)を推進している。
フレイル(転倒)予防に加え、近年多発している自動車運転事故(アクセル、ブレーキの踏み間違い)の抑止にも貢献できるとの考えからであった。日常生活に草履を導入するだけの「ながら運動」だが、足趾挟力(足指の踏ん張る力)が高まり踏ん張り力が高まった。また、立位時の足圧分布が変わり、踵荷重から前足荷重へと姿勢の改善も認められた。これらは転倒リスクとも深く関わっており、転倒予防の一つのツールとして草履は有効であることがわかってきた。そんな矢先の今回の震災であった。
2024年、元旦に発生した能登半島地震後、多くの者が避難所生活を送っており、明らかに平常時とは異なる生活を強いられていた。他人の迷惑にならないよう「与えられたスペースから動かない」「じっとしている」など不活動になっていた。特に高齢者はこの傾向が強く、ADL(日常生活を自分自身の力で送るための能力)が低下し、避難所生活をきっかけに要支援・要介護状態になるケースもみられた。避難所ではスリッパを履いている者が多く、特に高齢者は“すり足”になっており、どんどん足腰が衰えていた。実際、現地調査を行うと足趾挟力および内転筋力(下肢の支える力)の衰えが認められた。
そこで、石川県立大学体育学研究室の宮口和義教授が推奨する鼻緒のある草履サンダルを避難者に提供したところ「足指が開き、気持ちがいい」「姿勢が良くなり、歩きが変わった」と喜んでいただいた。プロジェクトの一環で制作した草履を履いて行う『Foot活体操』も紹介した。半年後に健康チェックに行くと改善傾向が認められた。同様の取り組みを二次避難所となっていた野々市市老人福祉センターや加賀市の温泉ホテル施設でも行った。館内ではスリッパやシャワーサンダル等を履く者が多く、足部機能が衰えていることに気づいていないようで、測定結果に驚いていた。
また、「青竹踏み」は足裏及びふくらはぎの血行を良くする効果が知られ、むくみや冷え性に効果があるとされている。頻尿が改善したとの医学的検証結果も出ており、トイレが遠い避難所には極めて有効と考えた。そこで、金沢市の小学校でメッセージを添えた青竹を制作し、避難所に届ける活動も行ってきた。
避難所では神経を使うことが多いが、この事業に関しては自治体も積極的に応援してくれ、何よりも避難者に「気持ちいい」と喜んでいただいた。活動の様子はメディアでも大きく取り上げてもらった。意外と盲点であるが「避難所での履き物による身体への影響」を世間に啓蒙できたといえる。草履導入半年後に再検査に行ったが、姿勢の改善効果が確認できた。仮設住宅への移行が進んでいるが、引き続きサポートしていきたい。
(石川県立大学体育学研究室 教授 宮口和義)