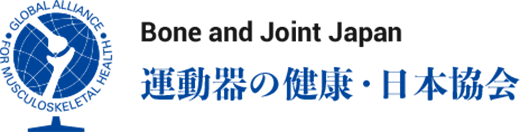2025年度 運動器の健康・日本賞
審査委員による選評
当協会では、今般の審査にあたり、下記の11名による審査委員会で厳正な審査を行いました。
- 審査委員
-
三上 容司専務理事 独立行政法人労働者健康安全機構 横浜労災病院 病院長稲垣 克記理事 昭和大学病院附属東病院 客員教授竹下 克志理事 自治医科大学 医学部整形外科 教授武藤 芳照理事 東京大学名誉教授/(一社)東京健康リハビリテーション総合研究所 所長吉井 智晴理事 東京医療学院大学 保健医療学部 リハビリテーション科 教授田尻 康人理事 地方独立行政法人 東京都立病院機構 東京都立広尾病院 病院長早野 晶裕エーザイ㈱ エーザイ・ジャパン 製品戦略推進部 プライマリーケア室 室長柴田 展司第一三共㈱ 日本事業ユニット 医薬営業本部 プライマリ・マーケティング部 骨関節・ペイン・感染症グループ グループ長鶴田 光利久光製薬㈱ 執行役員 医薬事業部 事業部長江波 和徳共同通信社 編集局スポーツ企画室委員中村 幸司NHK解説委員室 解説委員
- 運動器の健康・日本賞 選評
- 応募事業・活動の名称
- 足元からの健康づくり 能登Foot活(復活)支援事業
- 応募団体・個人
- 石川県立大学体育学研究室 宮口和義、恵寿総合病院
地震、津波、台風、火山噴火、洪水など様々な災害が毎年のように起きる災害大国、日本。そして、そのたびごとに、TVに映し出される被災者の姿に胸を衝かれる。整然と秩序正しく行動する被災者の方々に頭が下がると同時に、避難所で動けず、徐々に体力、健康を奪われていく高齢者の方々に思いを及ぼさずにはいられない。
石川県立大学の宮口氏を中心とするグループは、地域の医療機関と連携して、2019年から草履サンダルを用いた足育活動を開始した。フレイル予防、アクセル・ブレーキの踏み間違いによる自動者運転事故の抑止などを目指したものであった。草履サンダルは、鼻緒のあるサンダルで、これを履くことで、足趾挟力(足趾を踏ん張る力)が高まることや、立位時の加重分布が変わることが確認された。
このような活動を実践しているさなか、2024年1月1日に能登半島地震が発生した。避難所で生活する高齢者を調査したところ、日常生活における活動が低下し、足趾挟力と股関節の内転筋力が低下していることが判明した。これに対して、草履サンダルを提供したところ、「足趾が開き、気持ちがいい」、「姿勢が良くなり、歩きが変わった」と好評を得た。同時に、草履サンダルを履いて行う簡単な体操、すなわちFoot活体操を紹介した。その後、避難所の高齢者の健康チェックを行ったところ改善傾向が認められた。同様の取り組みを石川県内の二次避難所にも広げた。また、「青竹踏み」が頻尿を改善するとの医学的検証結果を得て、青竹を小学校で制作しメッセージとともに避難所に届ける活動も行った。
災害大国日本において、避難所における高齢者の活動量の低下、健康障害の防止は、重要な課題となっている。本件事業が、能登半島地震という災害時に、それまで地道に行っていた足育活動を広く避難所に展開し、高齢避難者の健康改善に貢献したことを高く評価したい。まさに、日本賞にふさわしい事業である。
審査委員:三上 容司- 運動器の健康・優秀賞 選評
- 応募事業・活動の名称
- 高校運動部の選手・マネージャーのための「メディカルトレーナー講習会」
- 応募団体・個人
- 大阪医療福祉専門学校
本協会が、昨年度から、10年あまりの準備期間を経て、「認定スクールトレーナー(ScT)制度」を稼働させ、全国に130名の第1期生が誕生した。学校での児童生徒等の運動器の健康推進のための保健指導と予防教育が主たる活動であり、その基礎要件となる医療資格が理学療法士である。
本事業は、ScT制度の趣旨を先取りしたかのように、2016年より、教育機関に勤める理学療法士らが、連携・協力医師らの助言を得て、近畿圏の高校運動部の選手とマネージャー、顧問教諭・コーチらを対象に開催している講習事業である。運動器疾患・障害や熱中症・低体温症、女性アスリートの三主徴、スポーツ栄養学等の講義やテーピングや救急処置・応急処置、適切な靴の選び方・使い方、コンディションングの方法等の演習を実施している。
2025年3月には、大阪府の公立高校の入学試験日(部活動が禁止される)に講習会を設定するなど、種々運営上の工夫がなされていることも印象的である。
すでに1000名以上の講習実績を有し、受講者らが自身の運動部活動の中で、その得られた知識と技法を活用して、外傷・障害や事故の予防に結び付ける効果を発揮している。今後の地域でのさらなる展開が期待され、高校の運動部活動の安全・合理的な運営と指導が一層強く求められている現代に即した優れた教育・啓発活動であり、「優秀賞」にふさわしいと高く評価された。
審査委員:武藤 芳照- 応募事業・活動の名称
- 病気や障がいのある子と家族へ、スポーツ・芸術・文化を通じて世界観を広げられるような機会を提供する活動
- 応募団体・個人
- 特定非営利活動法人AYA
日本において難病や障がいを持つお子さんの社会参加は、法制度や企業支援などが十分ではなく極めて限られている。また教育においても特別支援教育や患者団体以外の活動では体験学習やイベント参加の機会は極めて少ない。本活動の主催団体である特定非営利活動団体AYAはそのような機会を提供している数少ない団体である。
AYAのホームページには、わたしたちは、スポーツ・芸術・文化との出会いや触れ合いを通して、病気と闘う子どもたちの世界観が広がる機会を提供します、という言葉とともに、楽しそうに活動に参加しているお子さんの写真が掲載されている。活動内容を見ると、スポーツ系、芸術系、文化系の各種支援を行っており、スポーツでは試合の観戦・応援のみならず、チームへの体験入団やチアリーダーとのダンス、スポーツ選手とのプレイなど、芸実ではピアニストとの演奏やプロの画家による絵画指導、日本舞踊の体験など、文化系ではプロ書道家による書道体験や武道体験、蕎麦打ちやサポートなしでは難しい遠方への旅行、海外の子供達との交流など非常にバラエティーに富んだ機会を提供している。何より子供たちや家族の状況や要望に合わせた対応をされており、参加者同士が交流できるような配慮をされていることが非常に素晴らしいと感じた。
活動は2022年1月からと比較的短期であるが、2年間で78回のイベントを開催し、のべ6,293人の参加実績(家族・ボランティア含む)があり、アンケート回答者の半数以上が初めての体験ができたと回答しており、参加者の外出への意識が高まる効果が得られている。
難病や障がいを持つお子さんとその家族にとってAYAが提供する活動は、社会参加への扉であり道であり乗り物でもある。運動器の健康・日本協会の優秀賞に相応しい活動であると評価されたことも頷ける。
審査委員:田尻 康人- 運動器の健康・奨励賞 選評
- 応募事業・活動の名称
- 地方都市における膝前十字靱帯損傷予防啓発プロジェクト:スポーツ傷害から選手を守る取り組み
- 応募団体・個人
- 弘前大学医学部附属病院リハビリテーション部・弘前大学大学院医学研究科リハビリテーション医学講座
スポーツ選手の華々しい活躍を「光」とすれば、ケガは「影」である。スポーツには、どうしてもケガがつきまとう。強い光を求めることは、影が濃くなる危険をはらんでいる。弘前大学の附属病院リハビリテーション部および大学院のリハビリテーション医学講座は、影の部分に注目した大切な取り組みを続けている。
弘前市内の女子バスケットボールの強豪高校を対象に、膝前十字靭帯(ACL)損傷の予防トレーニングを実践した。損傷の発生要因について説明するなどの教育啓発をあわせて行っていることは、選手らの自覚を促すことができる。3年間でACL損傷の発生率を大きく引き下げる成果をあげた。競技団体と連携し、取り組みを地域の高校生、中学生、そして指導者へと広げている点も高く評価できる。
スポーツに打ち込む者、特に将来のある若い世代にとっては、影となるケガを抑えてこそ、活躍した時の光が真に輝く。こうしたコンセプトの取り組みが、今後さらに多くの選手、多くの競技へと展開することを期待したい。
審査委員:中村 幸司- 応募事業・活動の名称
- 児童の前・後屈時腰痛発症ゼロを目指す取り組み
- 応募団体・個人
- 九州看護福祉大学・吉里雄伸/山鹿市教育委員会/山鹿市立菊鹿小学校
近年、外遊びがしにくい環境が広がる中、運動の機会が減少し、腰痛を訴える児童が増えている。本事業は、2021年に山鹿市立菊鹿小学校の全児童を対象に、腰痛の罹患状況を調査することから始まった。前屈時に腰痛を感じる児童は3%、後屈時に腰痛を感じる児童は13%に認め、5・6年生の約17%が腰痛を経験していることが明らかとなった。
以降、山鹿市教育委員会・小学校教員・理学療法士が連携し、毎年の調査と「行うべき運動」や「気を付けるべき姿勢」をまとめたポスターを作成し、教室などに掲示することで腰痛予防の啓発を行った。2023年からは体育の準備運動に「動的ストレッチ」を取り入れるなど、より効果的な対策をした結果、腰痛の保有率は5%にまで減少した成果が得られた。
本事業は、本会の基本理念である「動く喜び動ける幸せ」を体現する素晴らしい取り組みであり、今後のさらなる推進と地域拡大により、多くの児童の健やかな成長を見守っていただきたい。
審査委員:早野 晶裕- 応募事業・活動の名称
- 全国シルバーリハビリ体操指導士連合会交流会
- 応募団体・個人
- 全国シルバーリハビリ体操指導士連合会
超高齢社会において、高齢者の健康寿命を延ばし、地域住民が自発的に健康づくりに取り組むことは非常に重要なテーマであり、協会の基本理念である“終生すこやかに身体を動かすことができる「生活・人生の質(QOL)」の保証される社会”の実現に不可欠なものである。
この目的を達成するためには、健康教育プログラムの実施や運動の機会の提供、地域内でのネットワークの構築など、多様な取り組みが求められる。本活動では各地域で活躍するシルバーリハビリ体操指導士の養成によりボランティア活動が促進されるとともに、シルバーリハビリ体操指導士による地域での体操教室を通じた地域住民の健康と互いを支え合うコミュニティの形成に貢献されており、フレイルや介護予防に留まらず、地域全体の健康づくりを支え、地域に根ざした活動が全国に広がりを見せていることが高く評価された。今後も地域全体が健康で活力に満ちた社会になることを期待したい。
審査委員:柴田 展司- 応募事業・活動の名称
- 和のウェルビーイングNOSSを活用した、機能改善・維持に役立つ 運動習慣の普及活動
- 応募団体・個人
- 日本舞踊スポーツ科学協会
NOSS(にほん・おどり・スポーツ・サイエンス)は、日本舞踊の「和」の動きをもとに、スポーツ科学を融合させた革新的なエクササイズプログラムである。必要不可欠な3大運動(有酸素運動・筋力トレーニング・ストレッチ)をバランスよく組み込んでいることが特徴としてあげられる。
普段着でも実践でき、年齢や性別を問わず、子供から高齢者まで幅広い層が楽しめ、さらには要支援・要介護の方や車椅子利用者にも実践可能な柔軟性を持ち合わせていること、体験者の9割より、「続けたい」と回答を得ており「楽しいから続けられる」効果があること、そして、日本の伝統文化とスポーツ科学を融合させた独自のエクササイズとして、健康増進と文化継承の両面において社会に貢献していることを評価し、今回の受賞となった。
審査委員:鶴田 光利- 応募事業・活動の名称
- 多世代で地域の子どもの元気な育ちを支える里山探検活動
- 応募団体・個人
- 楽育ひろばtomi
地域の子どもの元気な育ちを考える活動を10年以上も継続されており、子どもが楽しむことはもちろんのこと、運営スタッフの皆さんも遊び心満載で楽しんでいる様子が申請書類から伺われた。「里山探検活動」は、子どもが心の底から安心して全力で遊びに没頭できる環境を整え、子どもが子どもらしく育つことを応援している。幼少年期に自身の興味や関心のまま思い切り体を動かすことは主体性を育てることにも繋がっている。
地域の特性である里山を生かした多様なプログラムは、「子どもたちが自分の好きなことを思い切りする」ことを支援するが、現代社会ではこのシンプルなことが大変難しく、かつ贅沢なものになりつつある。更に、運営スタッフには地域の高齢者や学生たちが参画し、多様な年代の交流の場ともなっている。このことは、運営スタッフの心身の健康にも繋がり、全てのひとが心豊かに健康になる貴会の活動は本会の理念と一致するところであり、今後の更なる活動の発展を願い、この度の受賞となった。
審査委員:吉井 智晴